仕事終わりにメルカリやヤフオクを開いて、気づけば夜中まで中古品をチェックしている。そんな方が年々増えています。「どうせなら、本格的にビジネスとしてやってみたい」と思ったときに、最初のハードルになるのが古物商許可申請です。
許可を得ずに中古品を売買すると、古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性も。
一時的に自宅の不要品を売るだけなら不要なケースも多いですが、仕入れて販売する“ビジネス”として行う場合は古物商許可申請が必須です。申請から許可まではおおよそ40日前後かかるため、開業予定日から逆算して準備を始めましょう。
本記事では、初めての方でも迷わず申請できる5ステップを解説していきます。
ステップ1:営業所を決める
古物商許可を取得するには、まず営業所(事務所)を決める必要があります。
「ECサイトだけでやり取りするから、わざわざ営業所はいらないのでは?」と思われがちですが、古物商の場合は必ず営業所が必要です。
これは取引トラブルや盗難品の疑いが出たときに、「ここに行けば責任者と帳簿にたどり着ける」という拠点を、あらかじめ警察に示しておく必要があるからです。
そのため申請者の実情にあわせて住所の選択肢はありますが、まったく所在地を出さずに営業することは制度上想定されていないといえます。
参考:古物営業法第18条
▽「自宅バレは避けたい…」よくある実例Q&A
Q.自宅住所を公開したくありません。それでも申請できますか?
気持ちはとてもよく分かります。ただ、結論からいうと、「どこにも住所を出さずに」営業するのは現実的ではありません。制度の仕組み上、どこか1つは「責任をもって管理している場所」を警察に示す必要があるからです。
一方で、営業所の候補としては、
・自宅の一室
・事務所として借りた部屋
・所有者の承諾がある家族名義の住所の一部
など、事情に応じた選択肢があります。
「この住所を営業所にしたい」と決めた住所が使えるかは、建物の契約内容や管理規約、間取りによっても変わります。そのため、営業所候補が決まったら、あらかじめ管轄の警察署で確認しましょう。
Q.賃貸で大家さんの承諾がもらえません。実家を営業所にしてもいいですか?
古物商の営業所として認められるかは、大きく次の2つのポイントがあります。
1.その場所を継続的に使える権利があるか(賃貸借契約・所有など)
2.所有者(ご家族など)の承諾を得られているか
ご実家を候補にするケースでも、実際に出入りして帳簿を管理できるか、所有者の承諾を書面で示せるかを確認されることがあります。
この場合も、建物の契約内容や管理規約、間取りなどで営業所にできる・できないが決まります。
実家を候補にするかどうかで悩み続けていると、その間は申請全体のスケジュールが止まってしまいます。
迷ったときは、「この住所を営業所にしたい」という候補をメモして、早めに管轄警察署で相談してしまった方が、結果的に時間のロスは少なくなるケースが多いでしょう。
Q. バーチャルオフィスの住所で申請できますか?
いわゆる「住所だけを貸すタイプ」のバーチャルオフィスは、古物商の営業所としてほぼ認められていません。理由は、「実際に行けば責任者や帳簿にアクセスできる場所」とはいえないため。
一方で、実際に入居して常駐できるレンタルオフィスでは扱いが変わることがあります。
そのため、オフィスの契約内容のパンフレットを持参し、あらかじめ警察署に相談するのがよいでしょう。
営業所に関する判断は、都道府県警によって異なります。つまり、「A県でOK」でも「B県ではNG」となる可能性があるということ。そのため、あらかじめ申請予定の警察署へ事前相談することが重要です。

ステップ2:必要書類の準備
申請にはいくつかの書類が必要です。
また、「個人申請」と「法人申請」では内容が異なります。
必要書類の詳細は、警視庁の「古物商許可申請」のページに記載があります。記載例も載っているため、ご自身で申請したい方は確認いただくとスムーズです。
参考:警視庁「古物商許可申請」
▽「ECサイトの準備がまだできていない…」よくある実例Q&A
Q.ECサイトがまだない状態でも、古物商許可の申請はできますか?
警視庁の許可申請書(記載例)でも示されているとおり、ECサイトが未開設でも申請自体は可能です。
申請時点でECサイトがない場合は、申請時には「用いない」という扱いにして、出来上がってからURLの届出を行う流れが示されています。
具体的な書き方や必要書類は、自治体によっても異なるため、あらかじめ管轄の警察署で確認ください。
Q.たくさん書類がありますが、どの書類の準備に一番時間がかかりますか?
実務上でネックとなりやすいのは「身分証明書」と「法人役員全員分の書類(法人の場合)」です。
身分証明書:
本籍地の市区町村でしか取れないため、遠方本籍+郵送だと数日~1週間程度かかる
法人役員全員分の書類(法人の場合のみ):
役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が必要なため役員数が多いほど時間がかかる
本籍が実家のままになっている場合、平日に実家の市区町村役場へ行くために有給が必要になるケースもあります。「ひとまず身分証明書だけは先に動かす」つもりで、早めに請求しておくと安心です。

ステップ3:申請書の作成
書類が揃ったら、古物商許可申請書(様式第1号その1)を記入します。
よくあるミスとしては、
・「番地」「号」など住所表記の不一致
・押印漏れ(とくに誓約書)
・管理者の記載漏れ
などがあり、これらは再提出の原因となります。一度の再提出で、少なくとも数日〜1週間はスケジュールが後ろにずれることを考えると、提出前に5分だけ落ち着いてチェックする時間は、十分もとが取れる投資です。
ステップ4:警察署への提出
営業所所在地を管轄する警察署(防犯係)の窓口に提出します。警視庁の「警察署一覧」のページから、営業所の所在地を管轄する警察署を探すとスムーズです。
手数料は、19,000円
支払い方法は、19,000円分の「収入証紙」で納付することが多いです。一方で、神奈川県警察のように「キャッシュレス対応」を行うところや「現金」等へ移行しているケースもあります。
手間をできるだけ減らすためにも、ご自身の営業所がある管轄警察署の支払い方法をあらかじめ調べておくと安心です。

ステップ5:許可証の受領
申請から審査完了までは、約40日かかるのが一般的です(混雑期は長引く場合あり)。
許可が下りたら、申請した警察署で直接受け取ります(郵送不可)。
ここまでで「古物商許可申請」は完了となります。しかし、古物商開業となるのはここからです。
許可申請を終えてからがスタート
許可が下りた最初の1週間で、次の4つだけは終わらせておきましょう。
1.営業所内に古物商標識の掲示
2.ホームページに必要事項の表示
3.古物台帳の備えつけ
4.本人確認義務への理解を深める
とくに、買取時には相手の身元確認が必須となるため、本人確認の義務を十分理解しておくことが大切です。
許可後の運用をいかにラクに回すか
古物商の申請自体は、ご自身で行う方も増えてきています。一方で、古物商の申請許可後にいかにラクにミスなく回すかが古物商開業の本番です。
そのため、次のような状況や不安がある場合は、行政書士などのプロに相談してみる価値があります。

本業が忙しくて、ルールを一から確認する「時間」がもったいない……
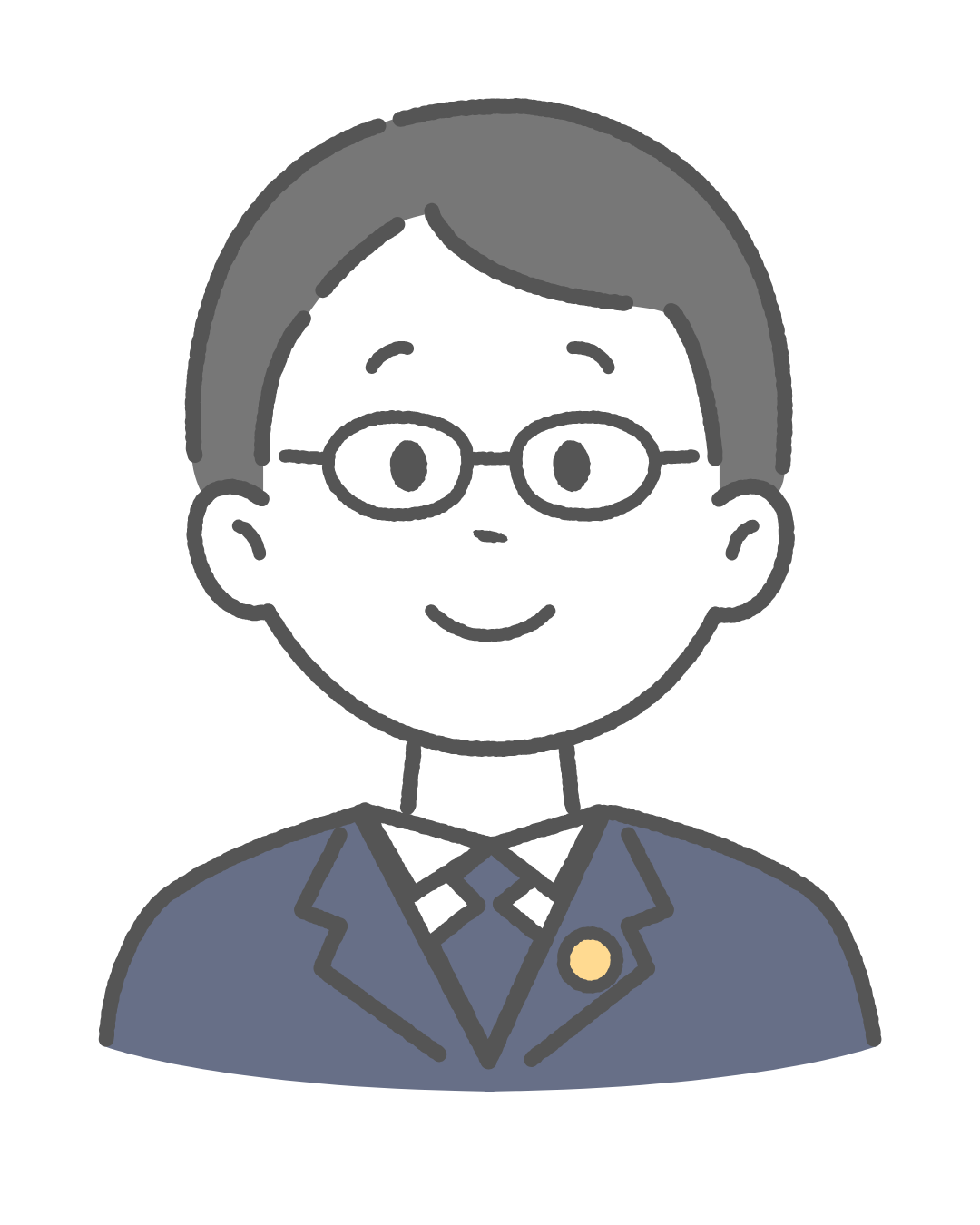
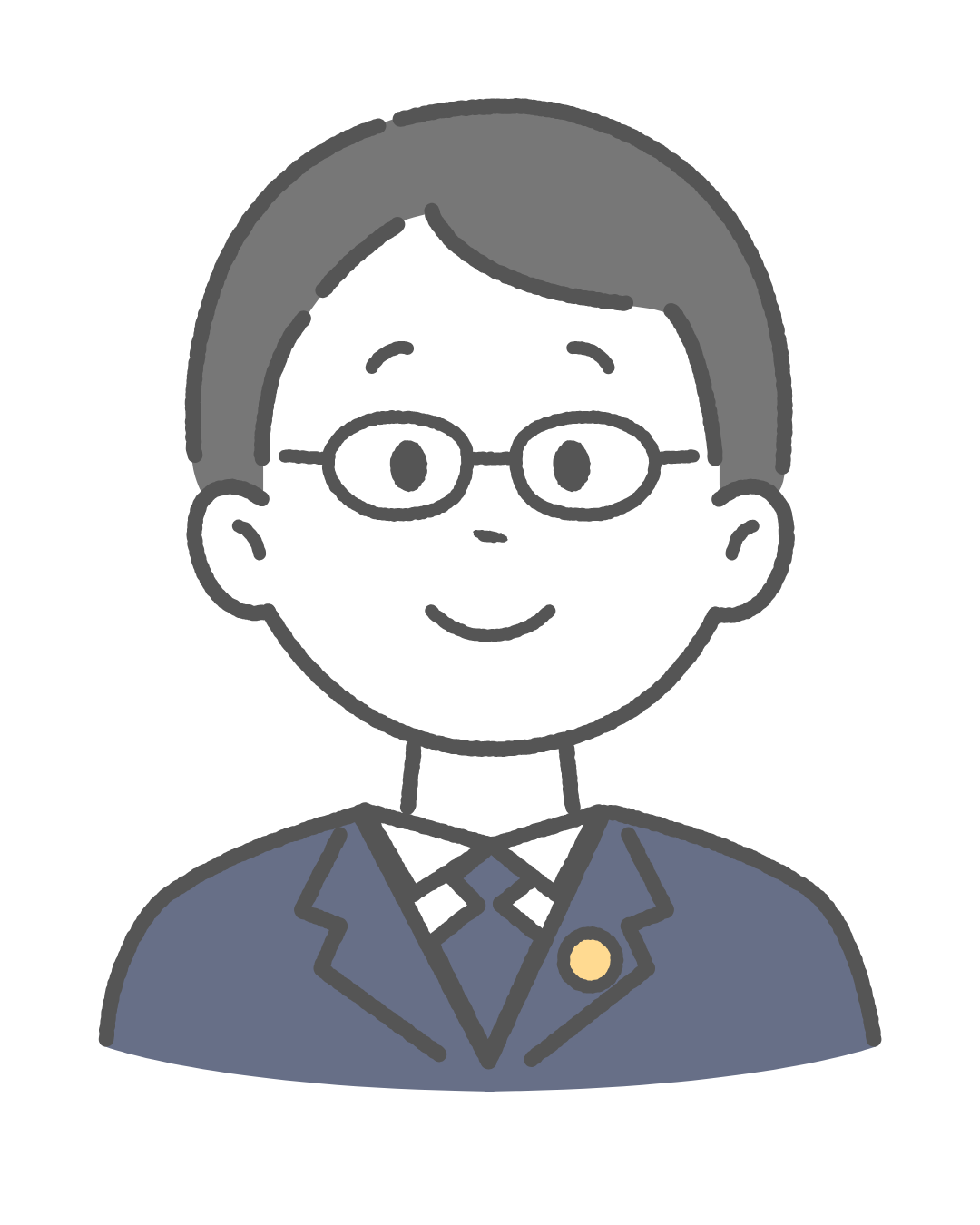
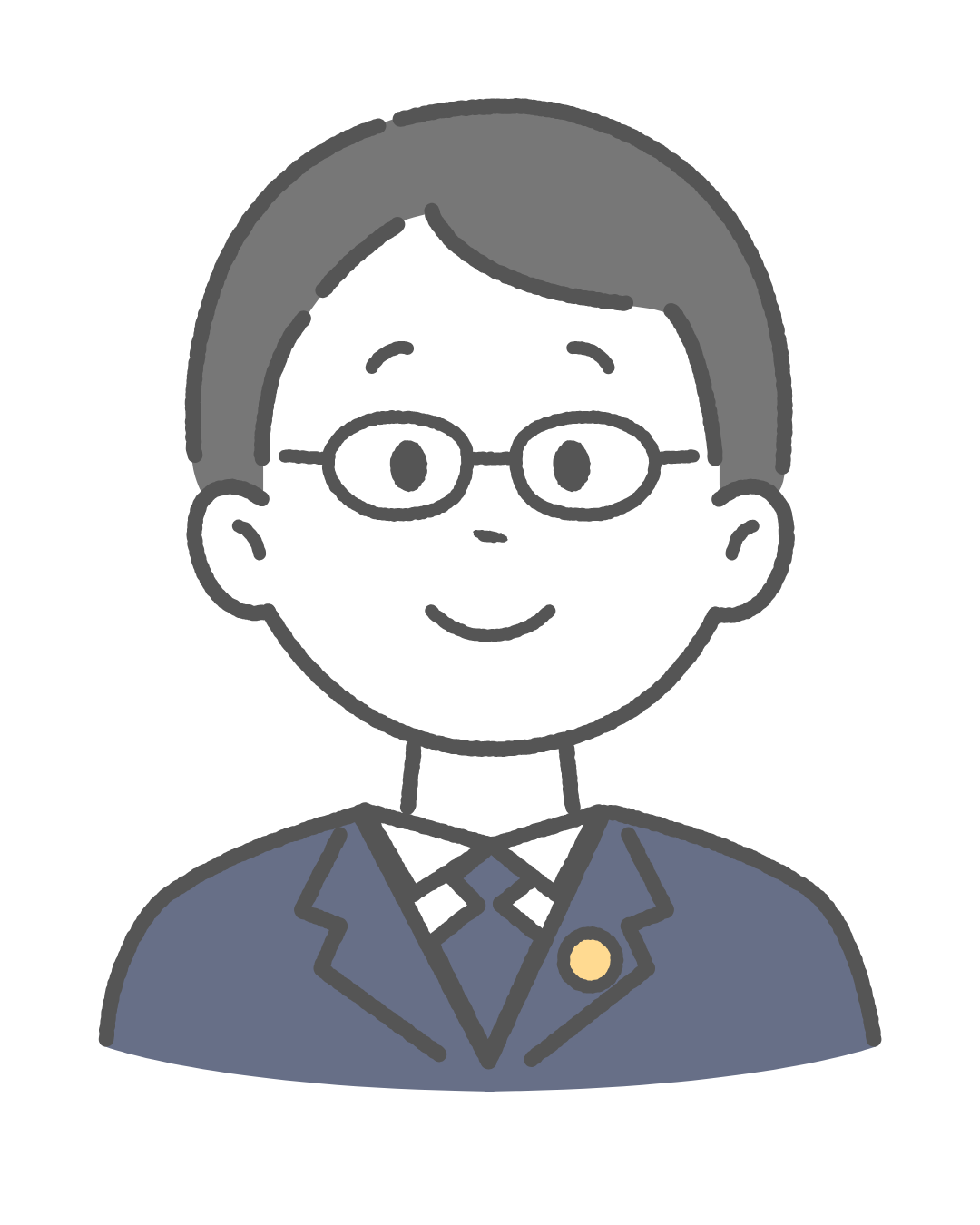
自分で行う場合、詳細を調べて進めると、トータルで40~50時間は平気でかかります。
仕事終わりに毎日2時間ずつ作業して、約1ヶ月の夜の時間が、まるっと申請手続きに消える計算です。
行政書士費用は4~5万円前後。
1~2ヶ月の夜時間を確保するか、1回の依頼で開業までのスピードをあげるか、で考えると判断がしやすくなるかもしれません。
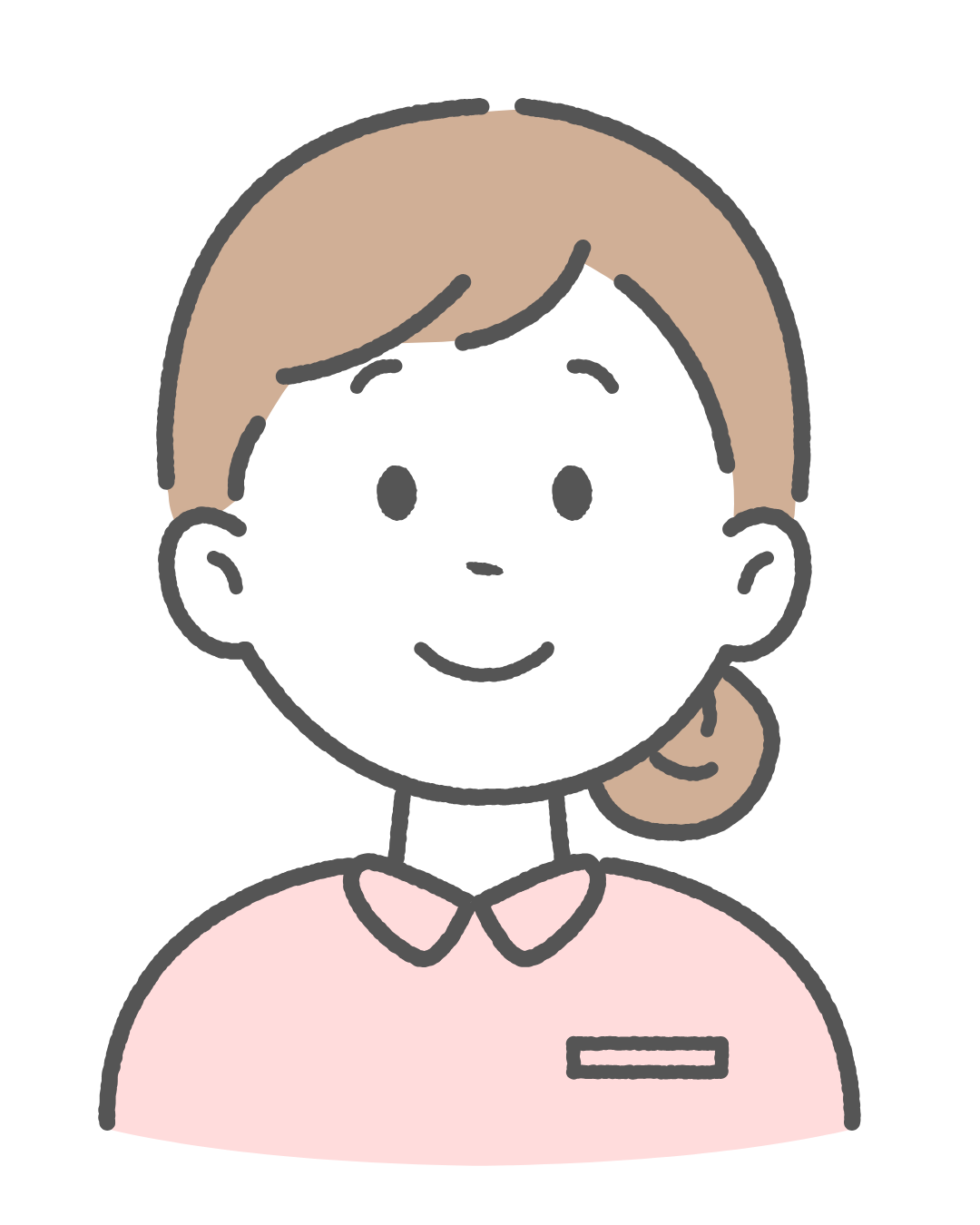
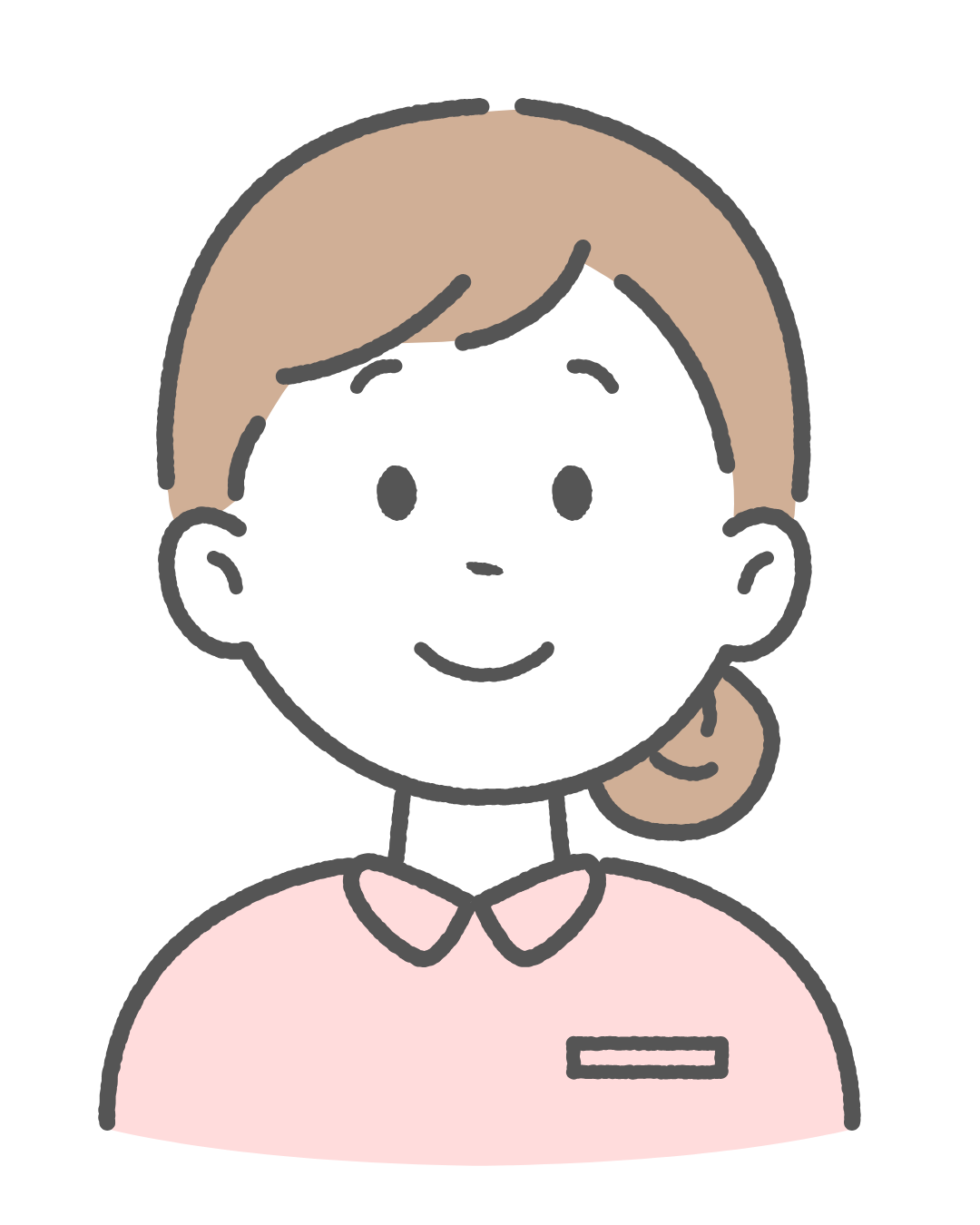
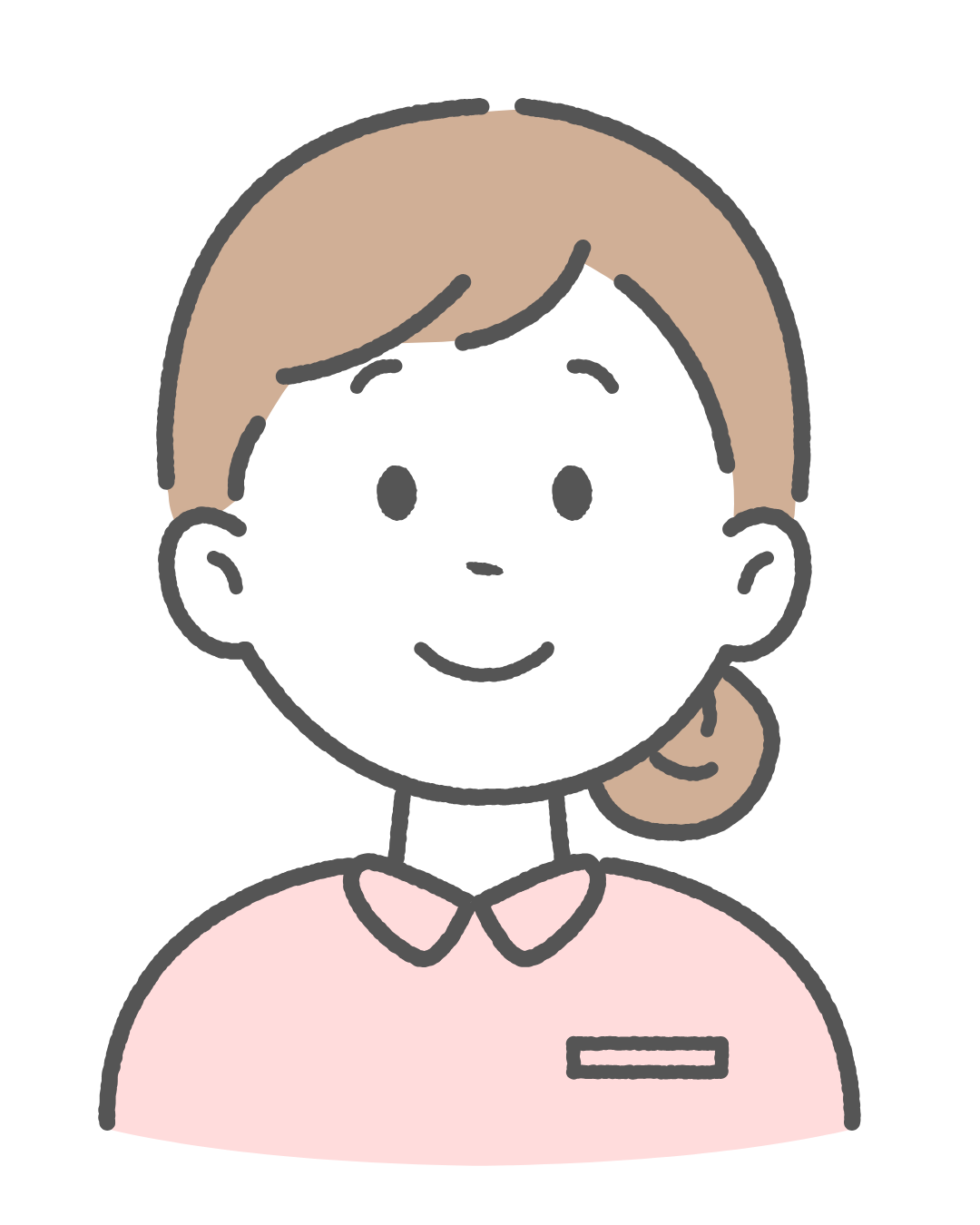
フリマアプリやECなど、オンライン特有のルールが不安……
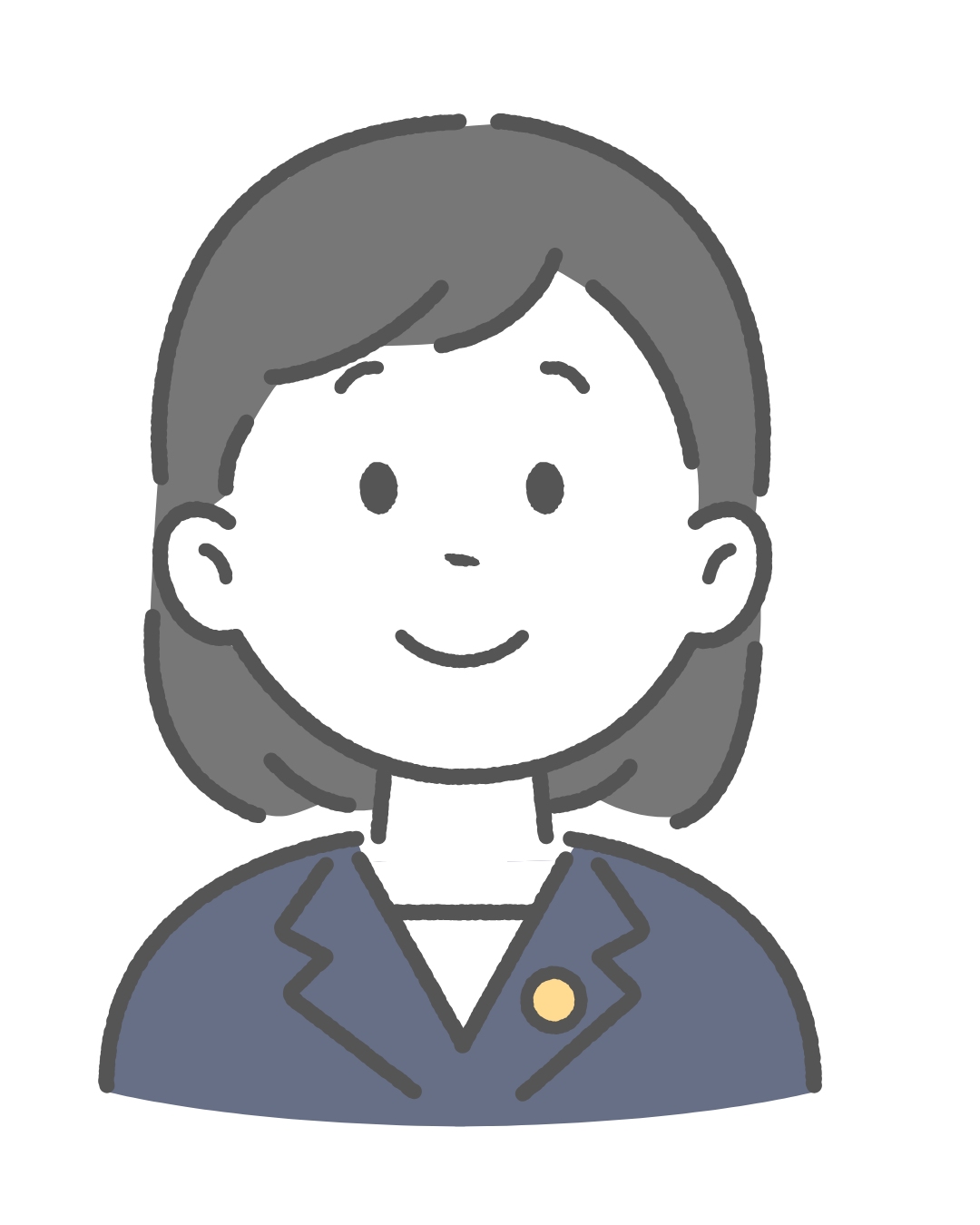
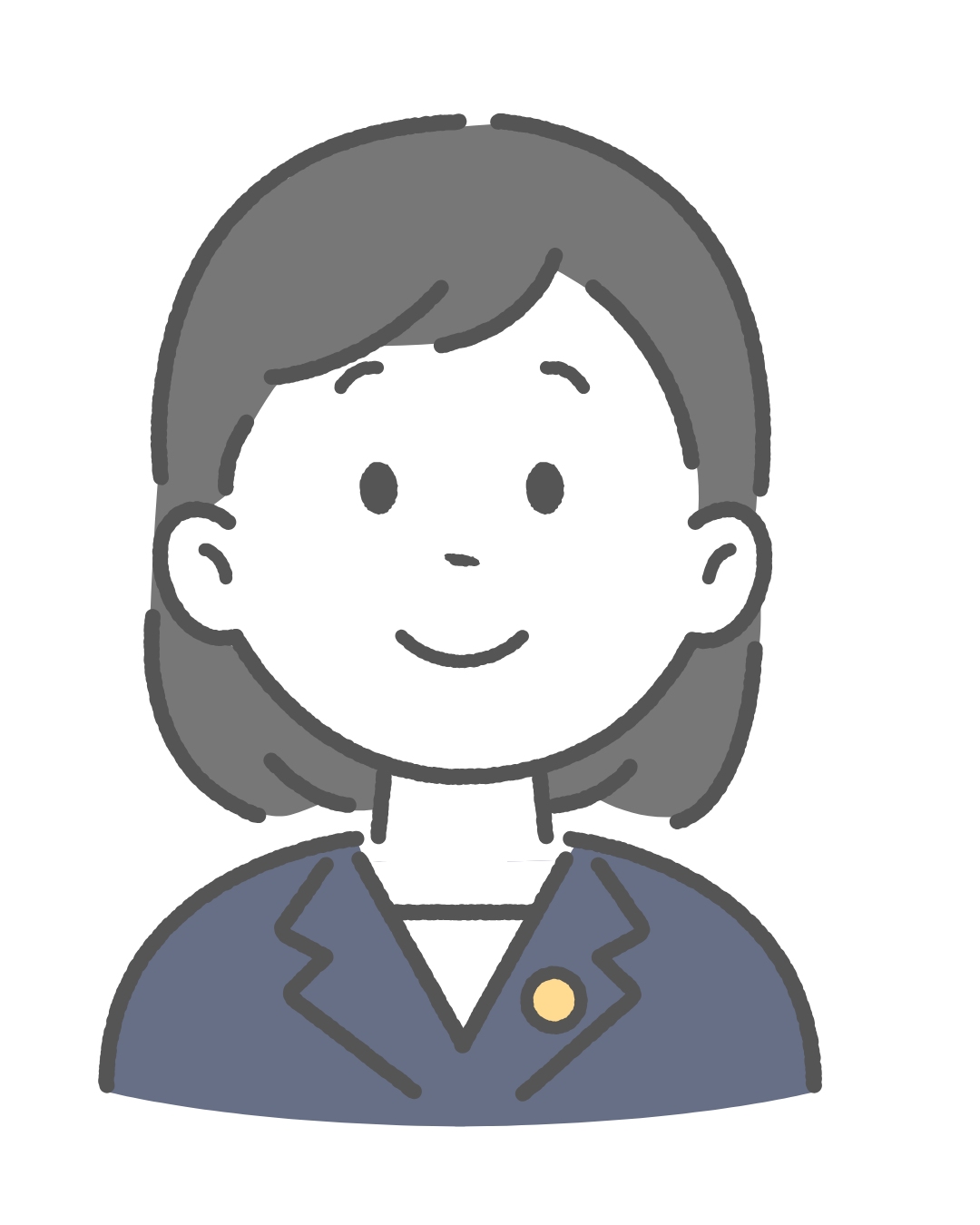
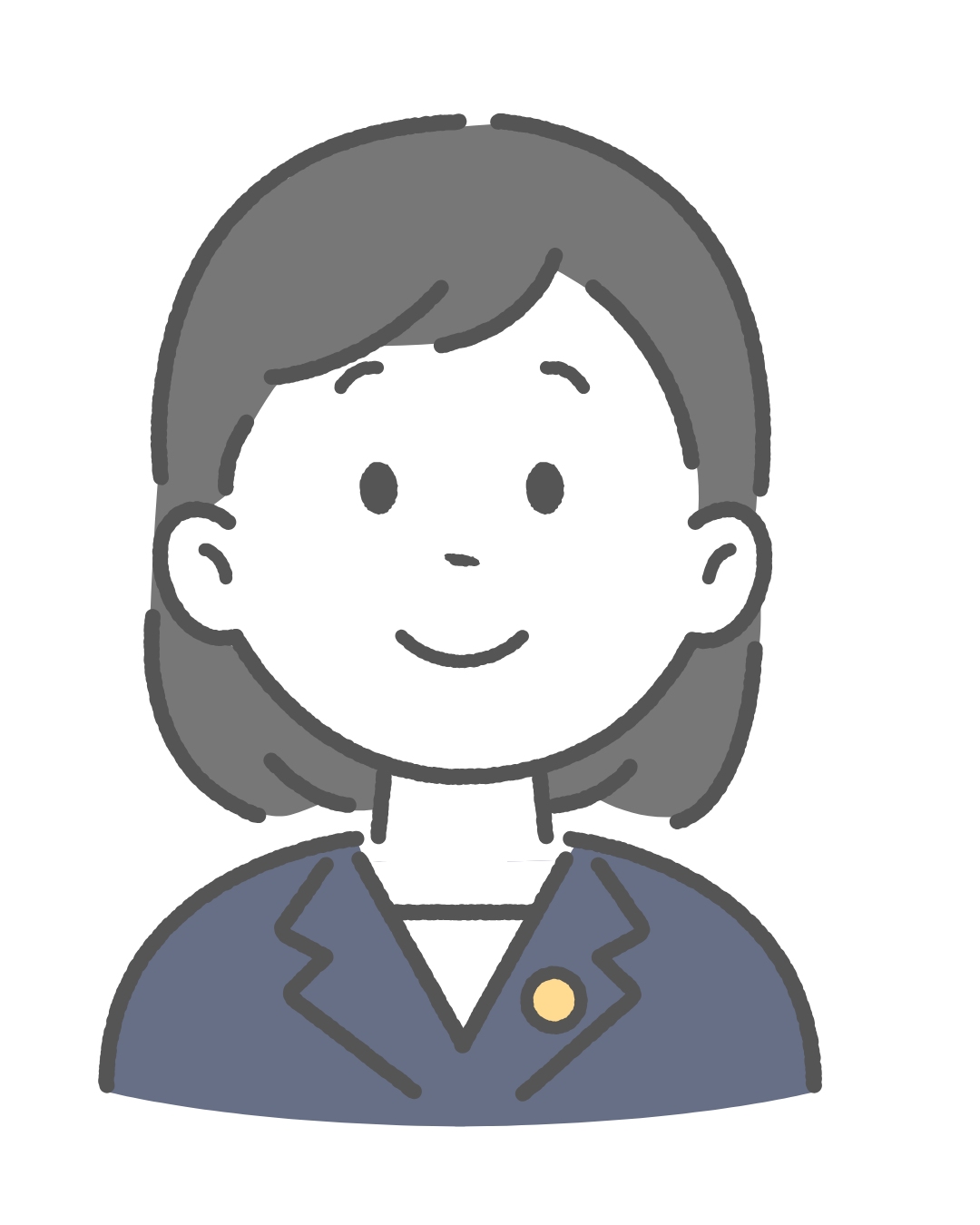
最初のフォーマットとマニュアルを整えておけば、あとはラクに取引が進められます。
「あらかじめ、相談できる場をつくっておくと安心できる」という方は少なくありません。
「自分でもやってみる。行き詰まったらすぐ聞ける」この状態をつくっておくと、開業後のストレスも一気に減ります。
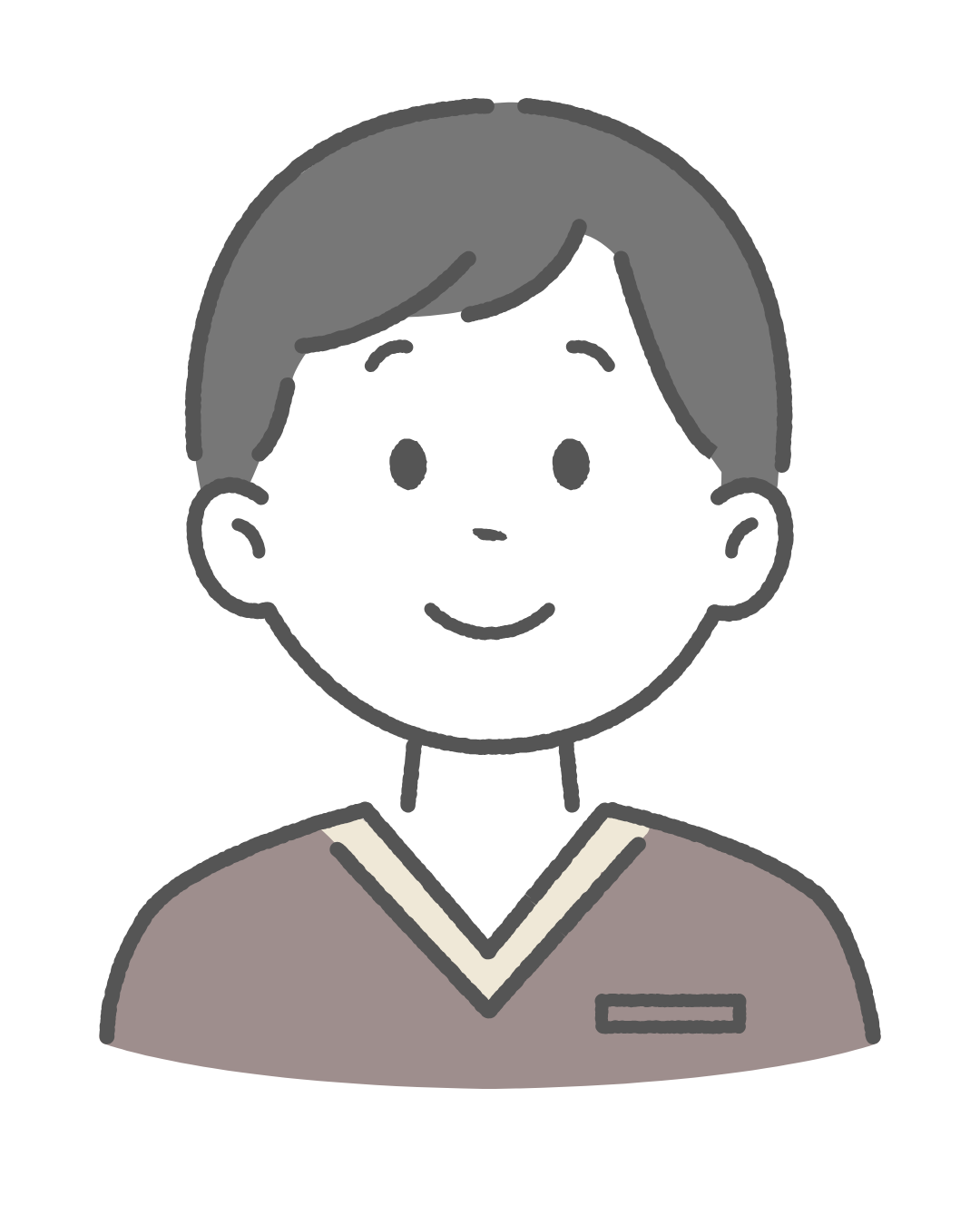
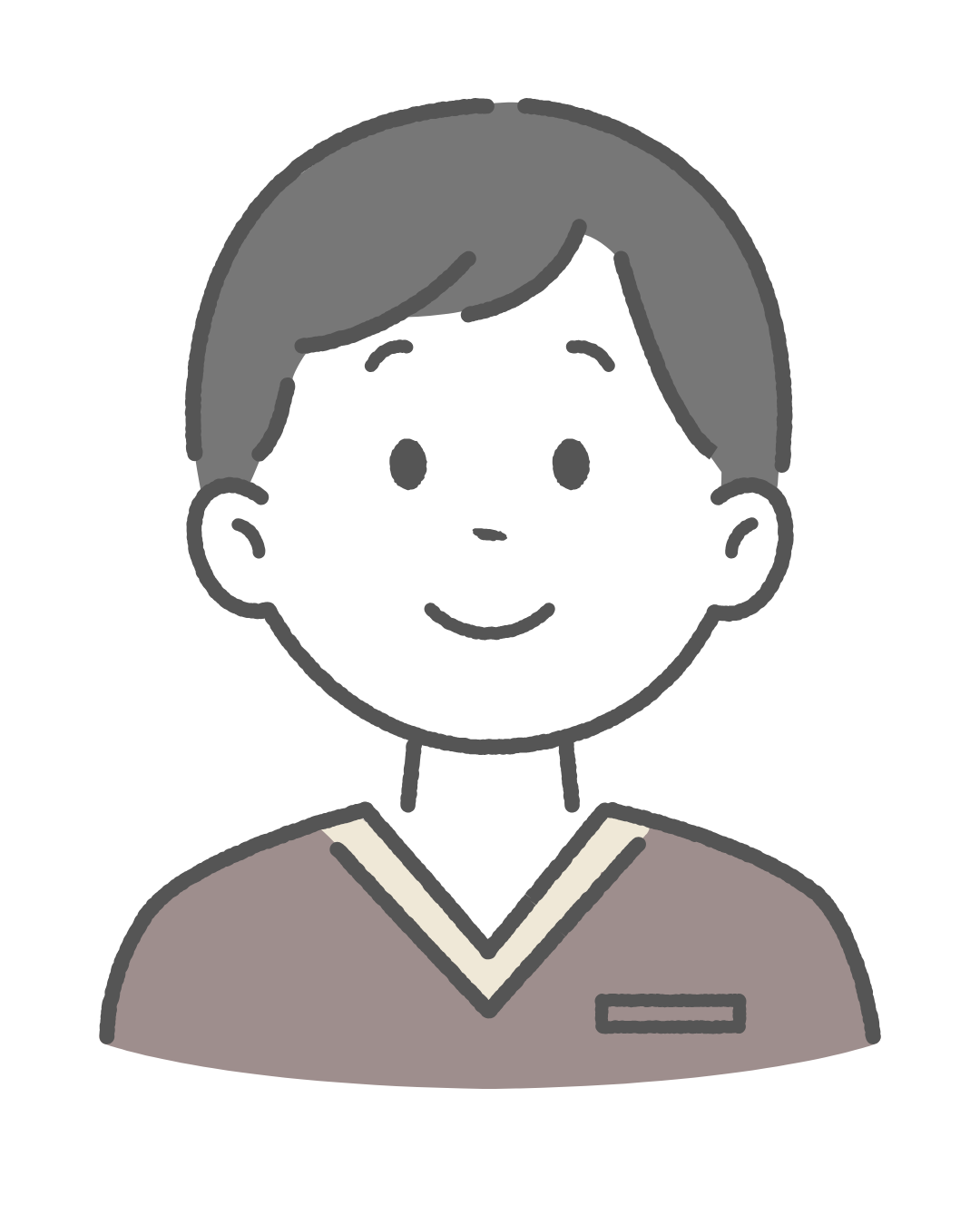
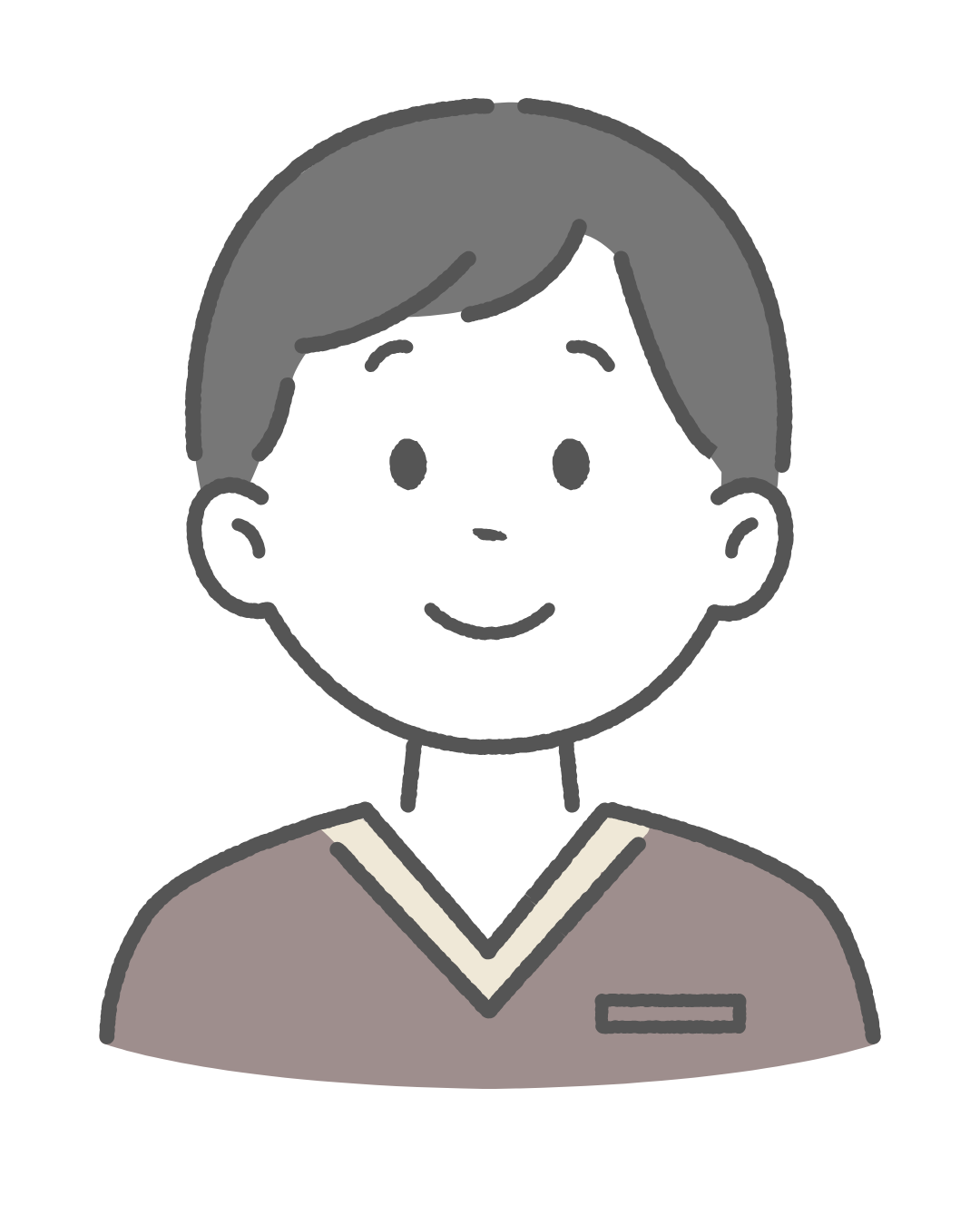
賃貸物件、バーチャルオフィス、法人役員多数など、負担が大きくなりそう……
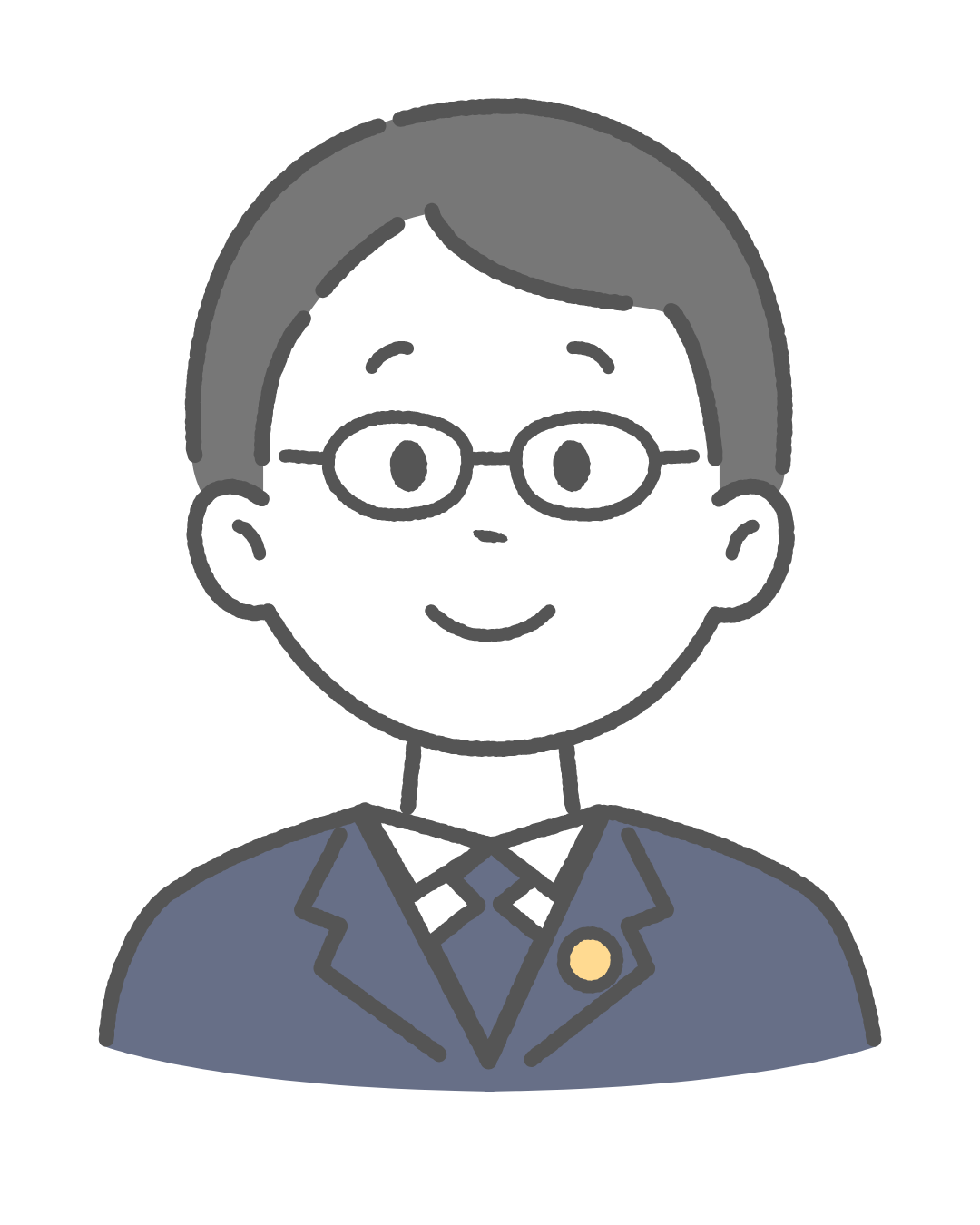
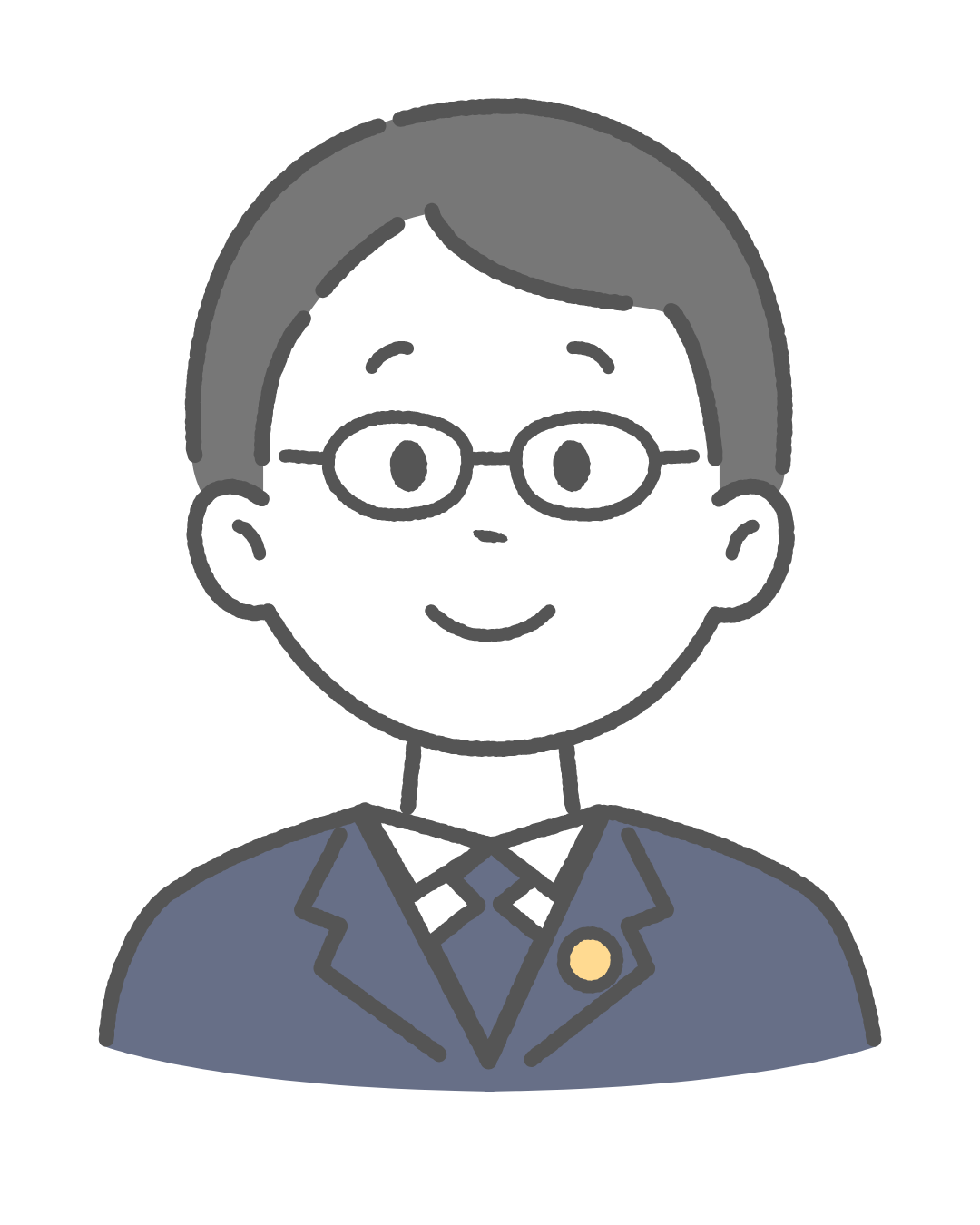
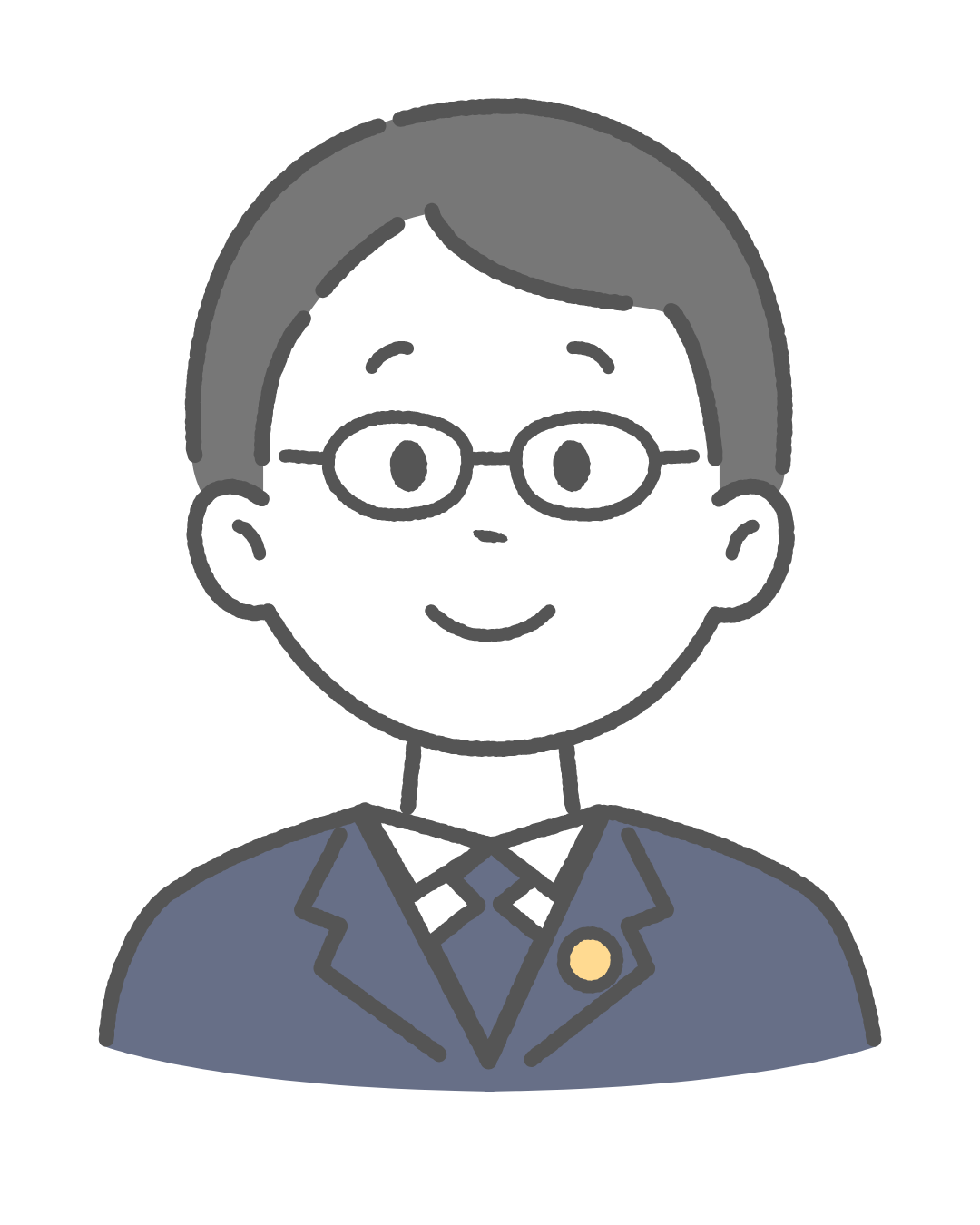
自分でも進められるけれど、「この書き方で落ちないかな?」と毎回ドキドキしながら手を動かすのは、正直しんどいものです。
途中でプロにチェックしてもらえば、不安で立ち止まる時間を減らして、安心してやるべきことに集中できます。
安心して事業をスタートするために
古物商許可の申請は、以下の5ステップで完了します。
①営業所を決める
②必要書類の準備
③申請書の作成
④警察署へ提出
⑤許可証を受け取る
一方で、必要な書類の取り寄せや不備の有無で、知らずに進めると思いもよらないところで時間をとられることが少なくありません。
とくに、個人と法人での申請で迷ったり、複数営業所をもつケースなどでは、確認作業が複雑になることも。
また、ご自身で申請する場合は、コストを抑えられますが「時間」と「正確さ」の両立が難しいこともあります。
こうしたロスをできるだけさけて、不安なく古物商開業をするためには行政書士などのプロに相談することも有効な選択肢です。
安心して事業を立ち上げたい方や時間のロスをできるだけなくしたい方は、プロへの相談を検討してみてはいかがでしょうか。
まずは「いつまでに開業したいか」と「どこを営業所にするか」の2つだけ決めて、無料相談でざっくりスケジュールを確認してみるところから始めてみてください。



